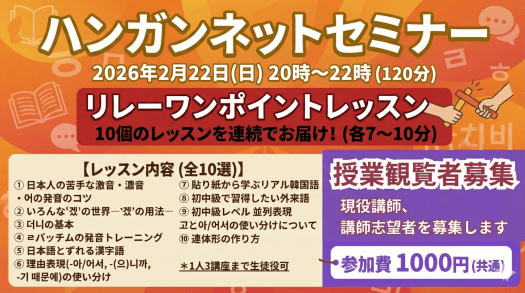=================================================
【週刊ハンガンネット通信】第570号(2026年2月18日発行)
「N잡러」加藤慧
=================================================
陰暦でも新年を迎えましたが、2026年の新たな挑戦として、年明けから週に2日、日本語学校に出講しています。コロナ前に日本語教育能力検定試験を受験し、対面とオンラインのプライベートレッスンで日本語も教えてきましたが、教壇に立つのは初めてのことです。また、非ネイティブ講師として間接法中心で教えてきた韓国語と違って、ネイティブ講師として直接法で教えるのも初めての経験です。
はじめはこうした違いに戸惑いもありましたが、基本的な授業の進め方は共通する部分も多いため、相乗効果でどちらの仕事にも活かせる学びを得られています。非ネイティブ講師とネイティブ講師、それぞれの視点から見えてくるものもあります。
また、日本語の構造や文法についての学びは、翻訳の仕事をする上でも強みになっています。
私が韓国語講師を始めるきっかけとなったのは、韓国留学中の言語交換でした。これが難しくも楽しく、帰国したら韓国語も教えてみようかな、と思ったのがすべての始まりです。その意味では原点回帰とも言えます。
いずれまた韓国の方に日本語を教えられたらとも思っていますが、現在の学生さんたちの出身国はネパール。簡単な挨拶や単語などを教わったり、文化について話してもらったりするうちに語学オタクの血が騒ぎ出してしまい、4月からは東京外国語大学のオープンアカデミーでネパール語を受講することにしました。
実はこれまでネパールという国について意識することはほとんどありませんでしたが、考えてみればコンビニや飲食店、そして見えないところでもたくさんのネパール人の方々にお世話になっているわけですし、すぐそばで日本の社会をともに生きる仲間です。互いの言語や文化についても理解を深めつつ、サポートし合っていけたらと思っています。
気づけば 3잡러 になってしまいましたが、〝ことば〟というキーワードを中心に、楽しみながら3本の軸のバランスをとっていきたいです。